満州国とは1932年(大同元年)から1945年(康徳12年)の間、
満州(現在の中国東北部)に存在した国家。

黄色は満州民族と統一、赤は大和民族と情熱、 青は漢民族と青春、白はモンゴル民族と純真、黒は朝鮮民族と決心を表す。
概要
1931年9月18日、
南満州鉄道(以後、満鉄)の線路が爆破された柳条湖事件を切っ掛けに満洲事変が勃発、
23万の張学良軍を相手に、わずか1万数千の関東軍により
5ヶ月という驚異の速さで日本本土の3倍もの面積を持つ満洲全土が占領される。
その後、関東軍主導の下に同地域は中華民国からの独立を宣言し、
1932年3月1日の満洲国建国宣言に至った。
元首(満洲国執政、後に満洲国皇帝)には
清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が就いた。
柳条湖事件は関東軍の謀略であった。
線路爆破を国民党の仕業と見せかけて満州占領の口実にしたのである。
満州事変、満州国建国を画策した張本人が
関東軍高級参謀の板垣征四郎と関東軍作戦参謀だった石原莞爾である。
実は石原莞爾も国柱会に所属する日蓮主義者であった。
満州国と日蓮主義の直接の関わりははないが、
満州国の国是である「五族協和」「王道楽土」の理想にその影響が見える。
万里の長城の外にある満州地域は漢民族の中国と明確に区別されており、
清朝の皇帝が国家元首になっているように、
ここを歴史的な故郷とする満州族の国家という名目で
一種の正当性を内外に示して独立したが、
五族協和という国是にあるように
アメリカ合衆国をモデルとした移民国家の顔を持っていた。
5族に含まれる日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人以外にも
ソ連・共産党から逃れた白系ロシア人や
ユダヤ人、ウクライナ人など多くの民族が共存した。
また、西洋の武による統治(覇道)ではなく、
東洋の徳による統治(王道)を訴えるなど
同じく国柱会の宮澤賢治の作品同様の仏教的ユートピア構想であった。
満州事変の意義
明治維新以来、日本は欧米列強に肩を並べるべく坂の上の雲を目指した。
脱亜入欧をスローガンに西洋化を推し進め、
日清日露戦争後に不平等条約が改正され、
第一次世界大戦を経て国際連盟の常任理事国入りを果たし、
名実ともに世界の五大国に数えられるようになったが、
列強と肩を並べるようになると
今までのような西洋の物まねや後追いをする訳にも行かず
目標を見失いつつあった。
国内においては関東大震災や天皇機関説。
国外においては世界恐慌や日英同盟の破棄、ソ連の誕生などの変化が現れ、
日本独自に対処すべき問題が現れてきた。
こうした時勢の中で多くの人びとが日蓮主義の影響を受けた。
第一次世界大戦後、日本は協調路線であったが、
世界恐慌の結果、ブロック化する世界に対して、
日本は西洋から再び東洋に目を転じ、
アジアの代表として東亜解放を主導し、凡アジア主義を掲げるようになる。
満州事変はまさに西洋に頼らない日本発の政治行動だった。
ただ、満州事変は関東軍の独断行動だった。
関東軍の行動は参謀本部や陸軍省など
陸軍中央の国防政策からも逸脱していた。
台湾軍や朝鮮軍などの方面軍は
基本的には内地の延長であり、日本領内を管轄とするが、
関東軍は海外常駐軍として独特の権限を有していた。
関東軍の独立性
関東軍は日露戦争後に領有した遼東半島南端の関東州の権益を守る存在であり、
満鉄拡大と共に組織拡大を続けた。
最終的には満州国と言う実質的な「独立国」を持つまでに至った。
板垣や石原の満蒙領有の考え方自体は陸軍内でも知られてはいたが、
関東軍の独断先行は国内でも波紋を広げ、
政府は当初から関東軍の謀略を疑い、国際社会に受け入れられないと判断し、
柳条湖事件発生の翌日には「戦線不拡大」を表明、
陸軍中央も政府に従い、「事変の拡大は避けよ」と関東軍に命令を下した。
政府(文民)が天皇の裁可を得ずに軍縮条約を結んだことは
統帥権干犯問題に発展し、浜口首相襲撃を呼び起こしたが、
関東軍(武人)は「自衛のため」と説明し、
この独断行動についても作戦中の判断とされ不問にされた。
しかし先述の通り、石原軍師の見事な采配と
張学良軍が正面から戦わなかった事、
国民党が共産党との戦いを優先し、日本軍の行動を静観した事により、
満州事変は驚異的なスピードで成功してしまい、
マスコミや世論は破竹の進撃を続ける関東軍を支持し、
ついにはソ連との緩衝地帯としての利用価値を見た
政府や軍中央もこれを追認する事になったのである。
一方、中華民国は国際連盟へ提訴し、連盟はリットン調査団を派遣。
日本の満州における特殊権益は認めらたものの
満州事変は日本の自衛行動ではないと否定された。
欧米列強は中国の門戸開放、機会均等を謳った九カ国条約違反であり、
「日本の中国侵略」としてこれを支持せず、
国際社会は満州事変と満州国を認めなかった。
日本はこれを不服として国際連盟を脱退、以後孤立化を進むことになる。
満州国の成功
主要な政治ポストは日本人が占めており、
事実上満州国は日本(関東軍)の傀儡国家であったが、
資源の少ない日本列島に対して満蒙一帯は豊富な資源が期待されていたため、
満州国は「日本の生命線」として国家予算を投入してインフラが進められ、
南満州鉄道のあじあ号を代表するように
極めて短期間に経済的文化的に発達した。
内乱が激しかった中国大陸で唯一安定した地域であったため、
日本のみならず中国からも多くの移民が満州に渡り、人口も増え続けた。
また、同じく国連を脱退したドイツ、イタリアの日独伊三国同盟や
国連不参加国のソビエトの日ソ中立条約などにより
結局、満州国は世界の独立国の三分の一以上から国家承認され、
アメリカやイギリス、フランスなど国交を結んでいなかった国でさえ
国営企業や大企業の支店を構えるなど、
人的交流や交易を行い国家としては安定した。
荒れた荒野に過ぎなかった満州は日本の資本によりビルや工場が立ち並び、
新京、哈爾浜、奉天、大連と言った主要都市は
「東洋のパリ」と称されるほどの賑わいだった。
満州国の最後
石原莞爾は皇道派でも統制派でもない「満州派」と呼ばれ、
反ソ、親中、知米と言う外交の基本姿勢を持ち、
中国から共産主義を追い出し、日満支が連携して対米戦に備える考えであった。
(世界最終戦争論)
石原の基本政策は皇道派とも共通しており、
戦中は予備役に追いやられた事で、
2.26事件で排除された皇道派と似た境遇でもあったが、
1936年の2.26事件当時、参謀本部作戦課長だった石原は
皇道派青年将校の気持ちに同情しつつも軍紀を乱した一点で、
他の将校が判断を渋る中で一貫して反乱鎮圧を訴えた。
石原はリアリストで戦略重視、テロの手法には反対だった。
満州国建国に深く関わった石原だが、
建国後は早々に中央に呼び戻され、運営にはあまり携わっていない。
1938年の支那事変においては中国との全面戦争に反対し、
東條英機との対立から予備役に追いやられ、政治の表舞台から姿を消す。
最後まで大陸の領土拡張や拙速な対米戦に反対していたが、
反米、反中、知ソの統制派主導のもと大東亜戦争が始まった。
満州国は大東亜戦争に正式参戦せず、
日ソ中立条約によってソ連とも領土保全が約束されたため、
戦争終盤までは目立った戦災に巻き込まれなかった。
末期は抗日ゲリラの活動も活発にはなっていたが、
関東軍はなるべくソ連を刺激しないように努めた。
戦争末期に連合国潜水艦による通商破壊で
南方資源の獲得が難しくなり、
太平洋の制海権・制空権を相次いで失い
連合艦隊が壊滅した事で日本海軍が講和に傾く中でも
満州国の鉱物資源生産数は向上しており、
中国戦線で連勝を続ける日本陸軍は継戦(本土決戦)を主張していた。
一方で日本政府は満州国の中立化を条件に
中立条約が有効であったソ連に連合国との講和の仲介を要請していたが、
既にヤルタ密約で参戦を決めていたソ連は日本の提案を無視した。
最終的に石原が最も恐れたソ連侵攻を許し、満州国は13年5ヶ月の歴史を閉じた。
満州に残されたインフラはソ連や中国など共産圏に渡り、同国の発展に寄与した。
まとめ
もし、2.26事件を起こした皇道派青年将校と
満州事変を成功させた石原莞爾がもっと早い段階で出会っていれば
満州事変以降の戦争を回避して、
満州国が現在においても健在だった可能性は否定できない。
満州事変と支那事変は全く別の動機であり、
満州国成立後は連盟への提訴と言う紛争はあったものの
塘沽停戦協定以降は、共産ゲリラや匪賊によるものを除き、
満州国と中華民国との大規模な武力衝突は無く、長城線を挟んで安定していた。
満州派も皇道派も中国への更なる侵略には反対だったため、
2.26事件によって昭和維新が成され、皇道派が政権中枢を担っていれば
支那事変も起こらず、日本は内向きな経済政策を優先しただろう。
石原莞爾は3年統治構想を持ち
近い将来に関東軍が満州国から手を引くところまで考えていた。
溥儀が清朝再興を目指したことは事実であり、
関東軍が撤退し、日本が国内問題解決を優先したら
満州族や現地国民による満州国運営が実現しただろう。
この広大な国家プロジェクトが完成していたら
満州国はアジア統合の象徴となり、
新京は今頃、ブリュッセルのような国際都市となっていたかもしれない。

(出典:梓地)
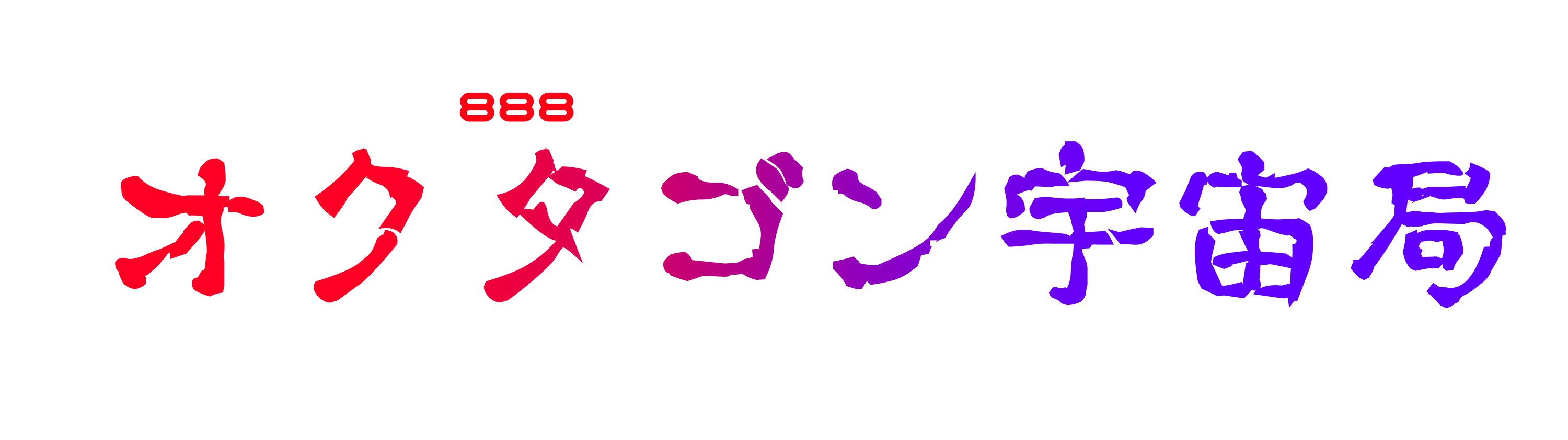
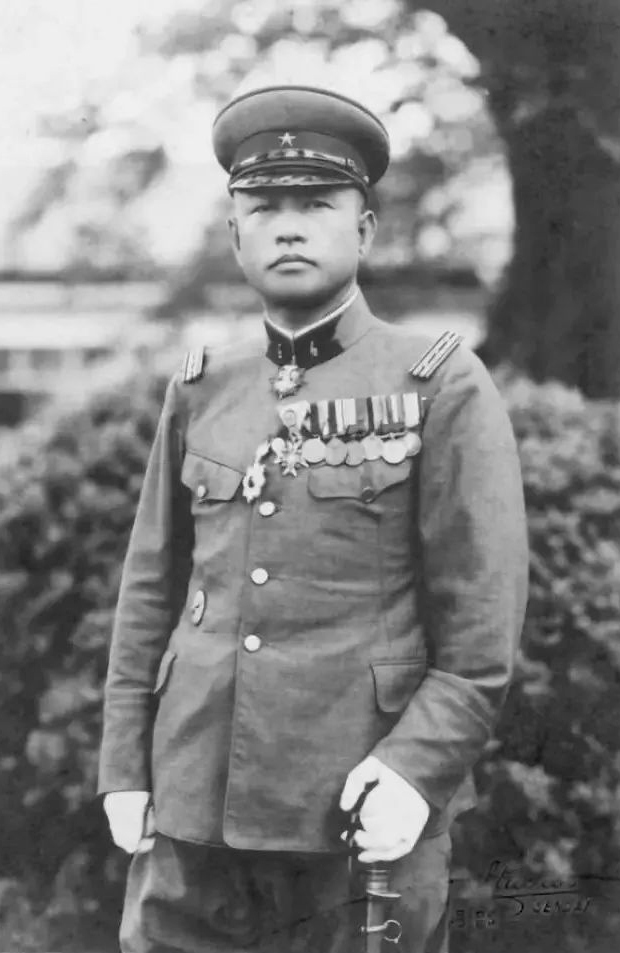




コメント
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
よくまとまってるじゃん。
石原莞爾は満州を第二のアメリカにしようとしてました。
まさにおっしゃる通りですね。
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
> pattonさん
この「第二のアメリカ」というのが
アメリカ自信最も許せなかったのじゃないかなと思ってます。
「河豚計画」で満州国は大々的にユダヤ人を匿う可能性もありましたしね。
実現していれば日米関係も変わっていたかもしれません。